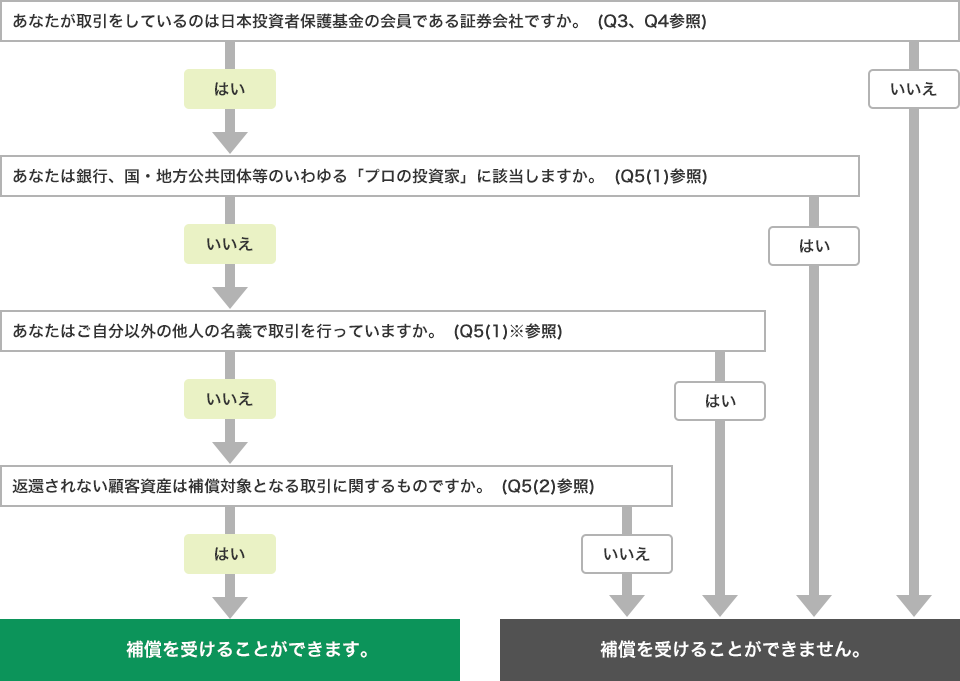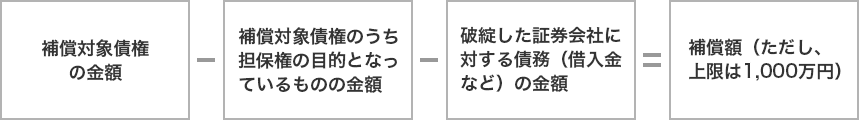店頭デリバティブ取引とは、「店頭」という言葉のとおり、取引所という市場に注文を出すことなく、先物、オプション、CFD取引について、お客さまと証券会社の間で相対で行う取引です。取引の種類としては、有価証券に関する先物、オプション、CFD取引、貴金属等の商品に関する先物、オプション、CFD取引等があります。
また、外国有価証券市場デリバティブ取引とは、デリバティブ取引のうち有価証券の先物、オプション、CFD取引を、国内の取引所ではなく、外国の取引所で行う取引のことをいいます。
これらの店頭デリバティブ取引や外国有価証券市場デリバティブ取引に係る金銭、有価証券などのお客さまの資産については、全て日本投資者保護基金の補償対象ではありません。(Q5(2)参照)
 信託受益権、組合契約などの第二種金融商品取引業に係る取引やFX取引は、日本投資者保護基金の補償対象ですか。
信託受益権、組合契約などの第二種金融商品取引業に係る取引やFX取引は、日本投資者保護基金の補償対象ですか。

信託受益権、組合契約などの第二種金融商品取引業に係る取引やFX取引については、日本投資者保護基金の補償対象ではありません。
(Q5(2)参照)
 総合取引所で取引されている商品関連市場デリバティブ取引に関する補償制度は、どのようになっていますか。
総合取引所で取引されている商品関連市場デリバティブ取引に関する補償制度は、どのようになっていますか。

総合取引所で取引されている商品関連市場デリバティブ取引に関するお客さまの資産(金銭・商品・有価証券・倉荷証券)については、日本投資者保護基金の補償の対象になります。
ただし、お客さまの取引先の会社が日本投資者保護基金の会員であっても、日本商品委託者保護基金の特定会員でもある場合には、商品関連市場デリバティブ取引に係る分について、日本投資者保護基金ではなく日本商品委託者保護基金が補償を行います。
日本商品委託者保護基金の特定会員については、日本商品委託者保護基金のホームページをご覧ください。
http://www.hogokikin.or.jp/meibo.htm
なお、商品のデリバティブ取引のうち、補償対象となるのは、総合取引所で取引されているものです。取引所に注文を出すことなく、お客さまと証券会社の間で相対で行う、店頭デリバティブ取引については、補償対象ではありません。
 証券会社の説明を信じて有価証券を買い付けましたが、証券会社の説明が虚偽であることがわかりました。この場合、わたしが被った損失についても基金は補償してくれますか。
証券会社の説明を信じて有価証券を買い付けましたが、証券会社の説明が虚偽であることがわかりました。この場合、わたしが被った損失についても基金は補償してくれますか。

証券会社が虚偽説明を行ったことにより生じた損害に対しては、基本的には証券会社の賠償責任の問題となります。
仮に、証券会社が破綻してしまって賠償できない場合でも、その損害は分別管理の問題に起因したものではないことから、日本投資者保護基金が補償を行うことはありません。
破綻した証券会社の破産手続等が行われていれば、お客さまは損害賠償請求権が債権として届け出されることで、その手続にしたがって損害賠償請求権について証券会社の残余財産から配当を受けることになります(配当を受けられるか、どれくらいの配当率になるかは、事案ごとに異なります)。
 どうして証券会社の不正行為による被害を補償しないのですか。
どうして証券会社の不正行為による被害を補償しないのですか。

各国の投資者保護基金は、証券会社が破綻し、顧客資産の取戻しができない場合に、証券取引の信頼性を維持するために、一定限度まで補償を行う機関であり、証券会社の不正行為全般による顧客の被害を補償するわけではありません。米国(SIPC)やカナダ(CIPF)、EU各国等の投資者保護基金も、基本的に日本と同じ考え方で設立されています。これらの基金は参加する健全な証券会社の拠出により運営されており、仮に不正行為一般を補償することとすれば、健全な経営をしている証券会社がそれを負担することになるほか、却って証券会社の不正行為を助長する可能性がある(モラルハザード)ため、そのような補償は行っていません。
米国投資者保護公社(SIPC - Securities Investor Protection Corporation)
カナダ投資者保護基金(CIPF - Canadian Investor Protection Fund)
 証券会社の分別管理の状況を知ることはできますか。
証券会社の分別管理の状況を知ることはできますか。

 証券会社で有価証券を買い付けましたが、その発行体が破綻してしまいました。この場合、基金は補償してくれますか。
証券会社で有価証券を買い付けましたが、その発行体が破綻してしまいました。この場合、基金は補償してくれますか。

有価証券の発行者が破綻等したために有価証券が無価値になったり、債務不履行により元利金の支払いが行われなくなったとしても、お客さまが被った損失又は損害は証券会社の分別管理の問題に起因するものではないことから、基金は補償を行いません。お客さまの権利は発行体の破綻手続において処理されることとなります。
 日本投資者保護基金が補償を行う旨の認定・公告を行っていない場合であっても、個別事案として基金に対し補償を求めることはできますか。
日本投資者保護基金が補償を行う旨の認定・公告を行っていない場合であっても、個別事案として基金に対し補償を求めることはできますか。

日本投資者保護基金は、金融商品取引法に具体的に定められており、基金が証券会社による顧客資産の返還が困難であると認定・公告を行った場合に、公告した届出期間内に支払請求書を提出したお客さまに対して補償を行うものとされています。
基金が補償を行う旨の認定・公告を行っていない場合、補償を求めることはできません。